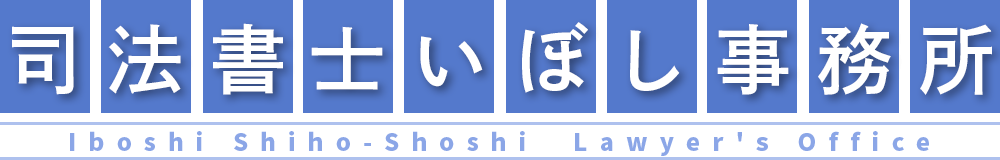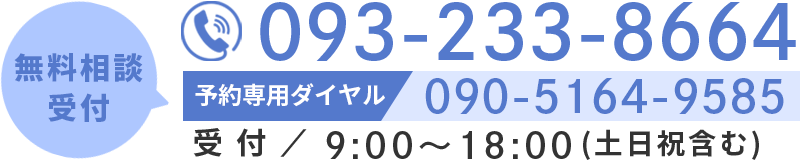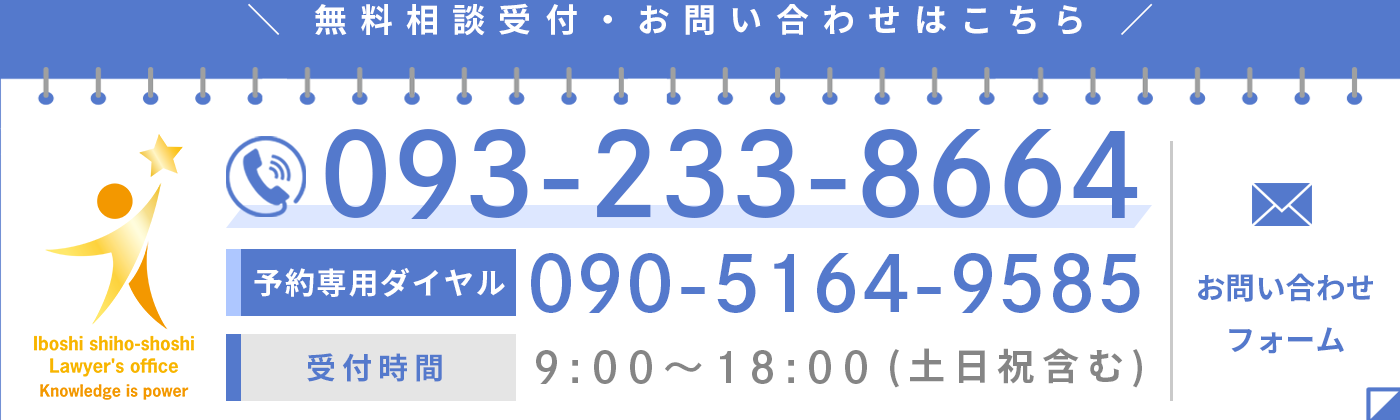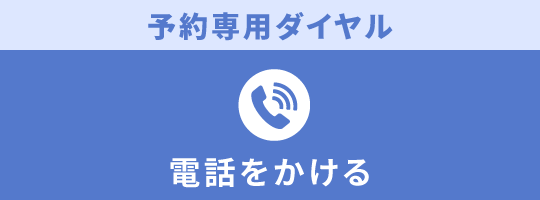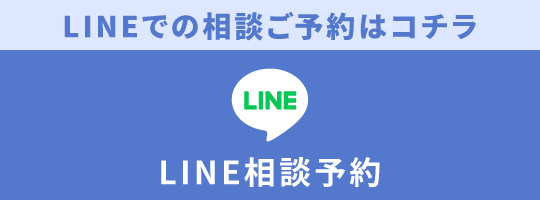借金が残っているときの相続方法に注意しましょう。
法定相続人である方でも「相続しない」という選択を取ることは可能です。亡くなった方が多額の借金を残しており、めぼしい財産もないときは、相続が大きなリスクとなります。そんなときは相続をしないために相続放棄を検討しましょう。
「相続放棄のやり方を知らない」という方も多いと思われますので、基本的な流れを参考にしていただければと思います。
■ 相続放棄をするとどうなる?
相続放棄が認められると、相続人ではないとの扱いを受けますので、当然借金を相続することもなくなります。消費者金融などから支払いを求められてもこれに応じる必要はなく「相続をしていません」と伝えれば良いのです。
■ 相続放棄の手続は3ヶ月以内にしないといけない
相続放棄の検討をしている方に注意していただきたいのが、相続放棄の期限です。民法で定められているように、相続放棄をするには「相続開始の事実と、自分が法定相続人であることを知ったときから3ヶ月以内」に手続をしないといけません。
遺産の調査に予想以上の時間がかかってしまうこともあるでしょう。そんなときは伸長を求める手続を必ず行うようにし、そのまま期限を過ぎてしまわないように気をつけましょう。
■ 相続放棄の手続方法
① 家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出
「相続放棄の申述書」を作成して家庭裁判所(被相続人が最後に住所を置いていたエリアを管轄する家庭裁判所)に提出しましょう。重要な記入欄が「申述の趣旨」と「申述の理由」です。なぜ放棄をするのか、そして相続財産の概略について記載します。
② 添付書類の準備も必要
相続放棄の申述書を提出するとき添付しないといけない書類もあります。
・ 被相続人の住民除票または戸籍附票
・ 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
基本的にはこれらの書類を準備しておけば良いのですが、申述人が第2順位あるいは第3順位の相続人である場合、先順位の相続人が亡くなっていることを証明するためにより多くの戸籍謄本等を集めていかないといけません。
③ 「相続放棄申述受理通知書」が発行される
被相続人が借金をしていた場合、債権者に対して相続放棄をした事実を通知しないと取り立てが続いてしまいます。そこで、相続放棄が受理されたときは「相続放棄受理通知書」が送付されますので、こちらを債権者に提出して相続放棄したことを認めてもらうこともできます。
【無料相談受付中】
公式LINE:https://lin.ee/32Xb3U1
Email:iboshi@ss-i-office.com
予約専用ダイヤル:090-5164-9585

福岡県北九州市にある司法書士法人井星事務所の代表、井星格充です。当事務所では、相続登記や遺産整理、生前対策、債務整理など、皆様の身近なお悩みに寄り添い、初回45分の無料相談を実施しております。JR西小倉駅から徒歩2分とアクセスも良好ですので、お気軽にご相談ください。